不妊症の検査って何をするの?よくある原因・高精度な「着床前診断」を紹介

妊活をしているのに、子供がなかなかできにくい場合もありますよね。そのような際に妊活の手助けになるのが不妊症検査です。不妊症の検査について、「実際にどんな検査をするの?」「痛みはないの?」といった疑問を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不妊症の検査は、月経の周期や既往歴などに合わせて、最適な方法で実施されます。検査の結果によってホルモンや子宮・卵管の異常、加齢による染色体異常といった原因が明らかになります。
本記事では、不妊症の検査方法をフェーズ別に紹介し、着床不全の際に行う専門的な検査、さらに染色体異常を直接調べられる高精度な着床前診断について解説します。
海外検査機関との連携で着床前診断をサポートする「グリーンエイト」のサービスについて詳しく知りたい方は グリーンエイトの着床前診断(PGT)・男女産み分けについて こちらのページをご覧ください。
目次
【フェーズ別】不妊症の検査方法一覧
まずは、月経周期の各フェーズに合わせて行われる不妊症の検査方法を紹介します。
月経期にはホルモン値の測定、卵胞期には卵巣や卵胞の状態確認、排卵期には精子と頸管粘液の相性を調べるフーナーテスト、高温期には子宮内膜の厚さや状態を確認する検査が代表的です。段階的に行うことで、不妊の原因を多角的に特定できます。
- 血中ホルモン検査
- 子宮卵管造影検査
- 経膣超音波検査
- フーナーテスト
- 子宮内膜測定
それぞれの検査内容について、詳しく解説していきます。
血中ホルモン検査
月経期に行われる「血中ホルモン検査」は、血液中のホルモン値を測定し、排卵や黄体機能に異常がないかを確認する検査です。
FSHやLH、エストラジオール、プロゲステロンなどを測定することで、卵巣機能の状態や排卵の有無を判断します。
ホルモンバランスの乱れは排卵障害や着床不全の原因になるため、早期の把握が有効です。
子宮卵管造影検査
「子宮卵管造影検査」は子宮や卵管の形態や通過性を確認するために行う検査で、月経終了後から排卵前の卵胞期に実施されます。
造影剤を子宮内に注入し、X線で撮影することで卵管の詰まりや癒着を確認できます。卵管障害は不妊の大きな原因の一つであり、この検査で問題が見つかれば治療方針の決定に役立ちます。検査自体は短時間で終わりますが、軽い痛みを伴う場合もあります。
経膣超音波検査
「経膣超音波検査」は、膣内に専用の超音波検査機器を挿入し卵巣や子宮の状態を観察する検査です。
卵胞の大きさを測定し、排卵のタイミングを確認する目的で卵胞期から排卵期にかけて行われます。
また、子宮筋腫や子宮内膜症の有無、子宮内膜の厚さなども評価可能です。放射線被曝がなく痛みも少ないため、不妊症の初期検査としてよく用いられます。短時間で繰り返し行える点もメリットです。
フーナーテスト
「フーナーテスト」は、性交後の頸管粘液中に精子が存在しているかを確認する検査で、排卵期に実施されます。
この検査で精子の数や運動性を観察することで、頸管粘液との相性を評価できます。精子が粘液中で動けない場合は「頸管因子」と呼ばれる不妊原因が疑われます。
シンプルな検査ですが、男性側・女性側の両方の要因を知る手がかりになり、人工授精や体外受精など次の治療ステップを検討する判断材料となります。
子宮内膜測定
「子宮内膜測定」は高温期に行われる検査で、着床に適した子宮内膜の厚さや質を確認します。子宮内膜が薄すぎると着床しにくく、不妊の原因となることがあります。子宮内膜の厚みは超音波検査や組織検査によって評価され、ホルモン補充療法などの治療方針につながります。
妊娠の成立に直結する重要な要素である子宮内膜の状態を早期に確認しておくことで、不妊治療の成功率を高めることができます。
いつでも実施できる不妊症の検査
先ほどは月経周期ごとの検査内容を紹介しましたが、周期に関係なくいつでも受けられる不妊症検査もあります。
代表的なのが感染症検査で、クラミジアや梅毒、HIVなど妊娠や出産に影響を与える疾患を確認します。その他に、以下のような検査があります。
- AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査
卵巣に残された卵子の数を推定でき、卵巣年齢の把握に役立ちます。
- 甲状腺機能検査
ホルモンバランスの異常が排卵障害や流産リスクにつながるため重要です。
- 風疹抗体検査
赤ちゃんの「先天性風疹症候群」を防ぐため、抗体を調べる検査です。
男性が受診できる不妊症の検査
不妊症の原因の約半数は男性側にあるとされており、男性の検査も欠かせません。
主な検査は精液検査で、精子の数・運動率・形態を確認します。異常が見つかればホルモン検査や精索静脈瘤の有無を調べる画像検査が追加されます。
男性不妊の多くは治療や生活改善で改善可能なため、早めに検査を受けることが大切です。夫婦で一緒に検査を進めることで、原因の特定と適切な治療方針につながります。
「なかなか着床しない……」という時に実施する検査
上記のような通常の不妊症検査で異常が見つからないのに、着床に繰り返し失敗してしまう場合には、専門的な検査が有効です。
ERA検査(子宮内膜受容能検査1)やERPeak検査(子宮内膜受容能検査2)では、胚移植に最適なタイミングを調べることができます。また、EMMA-ALICE検査や子宮内フローラ検査では、子宮内細菌叢の状態を解析し、炎症や感染が着床を妨げていないかを確認します。
こうした検査により、原因を特定し治療や移植計画の改善につなげられます。
しかし、これらのような検査でもなお発見できない不妊の原因として、染色体異常があります。
不妊・着床不全のよくある原因とは?

不妊や着床不全の背景には、さまざまな要因があります。原因は一つではなく複数が重なることも多いため、幅広い視点で検査を受けることが重要です。
例えば、ストレスや不規則な生活習慣、喫煙・過度な飲酒などはホルモンバランスや子宮環境を乱し、不妊の一因となります。また、慢性的な子宮内膜炎や甲状腺機能異常といった疾患も関係する場合があります。
特に、不妊・着床不全の原因として関係が強いのは母体の年齢です。加齢に伴い卵子の染色体異常が増え、流産や着床不全のリスクが高まります。
以下から、詳しく紹介します。
母体の年齢と不妊率の関係
女性の年齢は、不妊率や流産率に大きく影響します。
日本生殖医学会は、調査結果に基づいて以下のような見解を述べています。
女性の年齢が21~24歳のカップルの比率を1.00とすると、25~27歳では0.91、28~30歳では0.88、31~33歳では0.87、34~36歳では0.82、37~39歳では0.60、40~45歳では0.40と、加齢により自然に妊娠する割合が減ることが報告されています。
参考:日本生殖医学会_Q22.女性の加齢は不妊症にどんな影響を与えるのですか?
つまり、女性が40歳以上の場合、自然妊娠できる確率は20代よりも約60%低下するという計算になります。
「何歳から高齢出産になるの?」という疑問をお持ちの方は、以下の記事もご覧ください。
高齢出産は何歳から?リスクやよくあるお悩み、「着床前診断」の有効性を解説
不妊率が上昇する理由は染色体異常によるもの
年齢とともに不妊率が上昇する主な理由は、卵子の染色体異常の増加です。
卵子は生まれた時点から加齢とともに劣化し、分裂時に異常が起こりやすくなります。染色体異常がある胚は着床が難しかったり、妊娠しても流産につながるケースが多いためです。
特に40歳前後では染色体異常の頻度が高まり、妊娠継続が困難になることが知られています。
そのため、体外受精をした受精卵で染色体異常を検出できる着床前診断(PGT)は、高齢妊娠を希望する夫婦にとって有効な選択肢となります。
染色体異常を調べるには「着床前診断」
不妊や流産の原因として大きいのが卵子や精子の染色体異常であり、これを正確に調べる方法として「着床前診断」があります。
着床前診断では、体外受精で得た受精卵の一部の細胞を検査し、染色体や遺伝子に異常がないかを確認します。異常のない胚を選んで移植できるため、妊娠率の向上や流産リスクの軽減につながります。
加齢や不妊治療の反復不成功で悩む夫婦にとって、有効な選択肢のひとつです。
着床前診断のメリット
着床前診断には、以下のようなメリットがあります。
- 精度が高い
- 出生前診断よりもリスク・負担が少ない
- 遺伝性の疾患の有無も調べられる
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
精度が高い
従来の不妊症検査やスクリーニング検査では、間接的に異常を推測するにとどまる場合があります。一方、着床前診断では受精卵の遺伝情報を直接解析するため、染色体異常の検出精度が80〜95%と非常に高いのが大きな特徴です。
これにより、妊娠の成功率や継続率を高めることが期待されます。
出生前診断よりもリスク・負担が少ない
出生前診断は妊娠後に行うため、羊水検査や絨毛検査のように母体のお腹に針を刺すリスクが伴います。これに対し、着床前診断は妊娠前の受精卵を対象とするため、母体や胎児への身体的負担が少ない点がメリットです。安全性を重視する夫婦に適した方法といえます。
遺伝性の疾患の有無も調べられる
着床前診断の一部であるPGT-Mでは、特定の遺伝性疾患が遺伝していないかを調べられます。筋ジストロフィーや血友病など、遺伝性の重病リスクを回避できるため、家系に遺伝病のリスクを抱える夫婦にとって有効な選択肢となります。
健康な受精卵を選ぶことで、妊娠・出産の安心感を高めることができます。
着床前診断の実施は「グリーンエイト」にご相談ください

国内で着床前診断を受けられる人は限られており、「条件に当てはまらないため検査ができない」というケースも少なくありません。
そんな時に頼れるのが、グリーンエイトです。グリーンエイトでは、国内クリニックと海外の信頼性ある検査機関をつなぎ、渡航の必要なく高精度な着床前診断を受けられる体制を整えています。安全性と利便性を両立させたサポートにより、誰でも安心して検査を検討できる環境を提供しています。
グリーンエイトが選ばれる理由
グリーンエイトは、国内外のネットワークを活かし、高度な着床前診断を安全かつスムーズに実施できるサポート体制を整えています。最大の特徴は、信頼性の高い海外検査機関との連携です。国際基準を満たす施設での精度の高い遺伝子検査を実施します。これにより、国内だけでは難しい高度な診断を受けられるのが強みです。
また、グリーンエイトなら依頼主ご夫婦が海外に渡航する必要がない点も選ばれる理由の一つです。国内で採卵や体外受精、胚移植まで完結できるため、時間的・身体的負担を軽減できます。
さらに、グリーンエイトは生殖細胞輸送のプロフェッショナルとして、厳格な管理のもとで安全な検体輸送を実現しています。温度管理やタイムスケジュールにおいて徹底した品質保持を行うノウハウを持っているため、安心してお任せいただけます。
まとめ
不妊症の検査は、月経周期ごとに実施するものから、いつでも受けられる検査、さらに着床不全に特化した精密検査まで幅広く存在します。原因はホルモンバランスや子宮・卵管の状態、生活習慣、そして加齢による染色体異常など多岐にわたります。中でも染色体異常を直接調べられる着床前診断(PGT)は、妊娠率を高め流産リスクを減らす有効な方法です。国内では条件が限られますが、グリーンエイトなら海外検査機関と連携し、誰でも高精度な診断を受けられる環境が整っています。
Contact










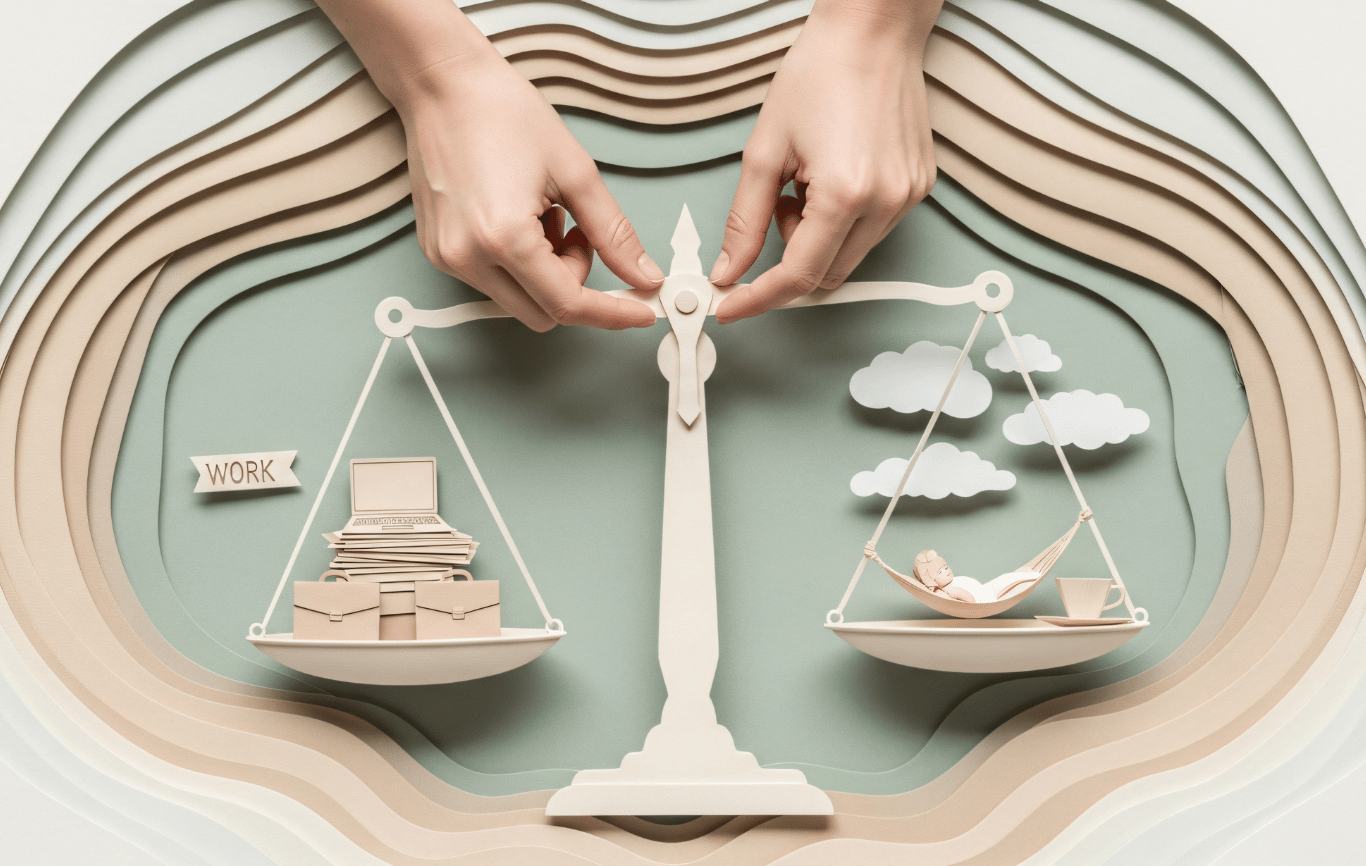


 資料請求
資料請求
 お問い合わせ
お問い合わせ
 LINEでお問い合わせ
LINEでお問い合わせ
 カウンセリング予約
カウンセリング予約